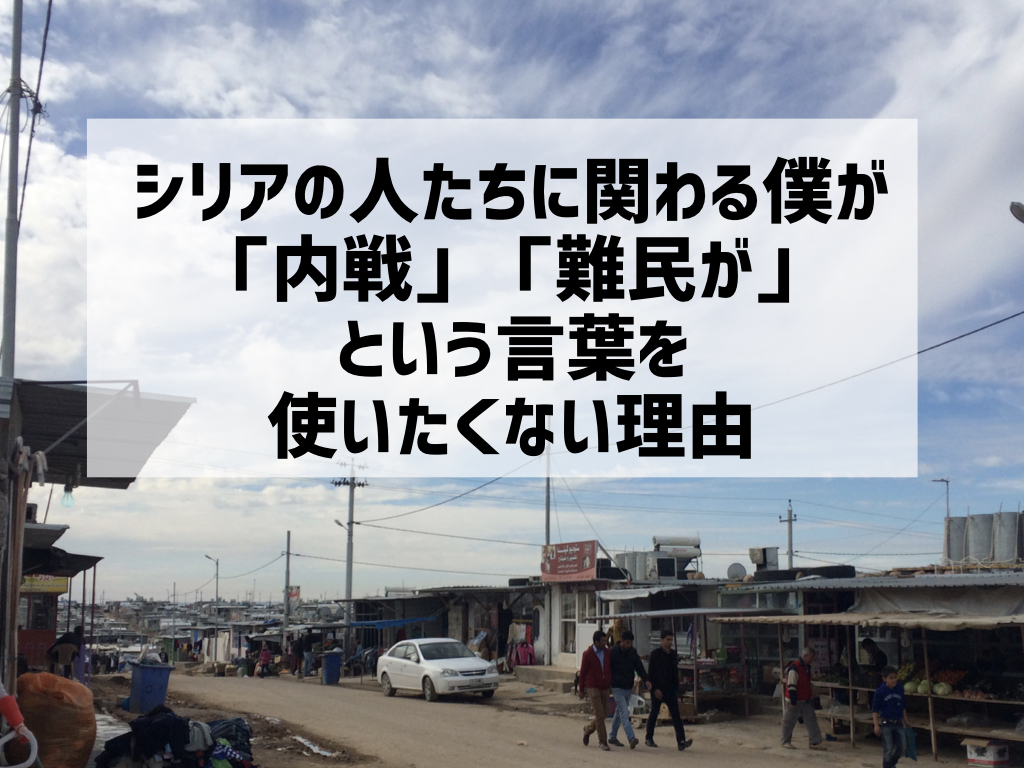シリアに関するイベントに参加したところ、
「内戦」
「難民」(という主語)
という単語に違和感がある自分に気付きました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━
内戦という表現が見失うもの
━━━━━━━━━━━━━━━━━
シリアで起こったのは「内戦」だったのだろうか。
なぜ「内戦」ではないのか…
「内戦」とみなすことで何が見えてなくなってしまうのか…
「内戦」という語を使うことで見落とされる事象のなかに、
シリア内戦が長期化し、解決が遅れている主因がある…
という、青山先生の表現に共感してるからかな、と思います。
僕個人の意見ですが、内戦という表現でシリアを論じるなかで「正義 vs 悪」という思考停止に陥りやすい表現になっているように感じるからです。
「内」ではなく「外」からの力学に、しっかりと目を向ける必要があると、僕は感じています
(そして、「外」の力は、罰せられることも、攻撃を受けることもない人たちです)。
(「外」について考える上でのオススメの本)






━━━━━━━━━━━━━━━━━
難民はアイデンティティ?
━━━━━━━━━━━━━━━━━
「難民の」「難民は」と、彼らを表すのが、不自然に感じました。
例えば10年前は、彼らは「難民」ではないし、ひょっとしたら明日にでも「難民」ではなくなるかもしれません。
(シリアに帰国するかもしれないし、市民権を取れるかもしれません)
「難民」というのは、彼らのアイデンティティというよりは「風邪」のような、一時的な状態のように思います。
そして何より「難民」と言われることを望まないシリアの人たちと、多く出会ったからです。
そうした視点から、個人の写真を見せながら「難民は…」と話すのに違和感がありました。
ただ「難民」という表現が持つ「チカラ」もあります。
言葉の中に「支援すべき対象」という意味が含有されてる「分かりやすさ」を持っているからです。
Piece of Syriaも「シリア国内の支援」がメインですが、「シリア難民支援をしてるPiece of Syriaの中野さん」と紹介されることが多々あるのも、そのせいかもしれません。
(個人としても団体としても、その活動もしてるので、間違いではないのですが…)
僕らがやりたいのは「難民」の支援ではなく、僕たちが好きになった「シリアの人たち」のお手伝いと思ってます。
(僕は誕生日プレゼントを考える、と表現してます。自分があげたいものではなく、相手が喜ぶものを贈るように。
もしくは、「困ってるから助ける」ではなく「好きなアイドルを応援する」ようなものになったら良いなぁ、と)

━━━━━━━━━━━━━━━━━
僕が何を伝えるのか
━━━━━━━━━━━━━━━━━
僕が伝える上で大切にしたいのは「考える」です。
けれど、こうしたSNSの文章って「考えない」ために読んだりもするように思います。
だから、リアルな空間でのイベントって大事だなぁ、と。
「戦争ってなんで起こるの?」
「平和ってどうやったら創れるの?」
「お金を渡す以外で出来ることはあるの?」
わかりやすい答えがない、世界の問いに、僕らはどう向かい合うか。あるいは、向かい合わないのか。
「考え続ける限り、逃げたことにはならない」
時に逃げても良いから、考え続けたい。
1人では見つけられない問いも、一緒に考え、向き合う仲間と出逢いたい。
そんな目的のために、伝えてるように思います。
そういう意味で、今日のイベントは、僕に「考える」機会をいただく良いイベントでした。